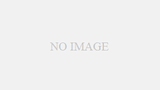こんにちは、くみです。
バンコクの旧正月はどんなものなんだろうーと中華街をふらふらしていたら(3日めなので遅い)、通りがかった中華街のお寺のワット・トライミット(Wat Trimit、タイ語でวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร)で無料の食事が振る舞われていました。
▼食事をもらう人々でごった返しています。

ちなみにタイトルの『飢えない国』というのはシーク教の寺院でごちそうになった事を友人に話した時に言われた言葉で、なんとなく気に入っています。東南アジアは飢えにくい…
中華街の様子
お正月を迎えて3日めのせいか、中華街自体はそんなに人もいなく、賑やかな感じはしませんでした。今考えるとお昼時で、人がワット・トライミットに集中していた可能性もあるのですが…
▼旧正月は赤と金がきれいでいいですね
ワット・トライミットで無料の食事
ワット・トライミットについて
ワット・トライミットはこのあたりです。中華街(ヤワラートのあたり)に行った事のある人なら目にしているのでは。
フリーミールを振舞っていることは全く知らなくて、なんとなくお寺に寄ってみようかな、という気持ちだけだったのですが…
人々が食べ物屋台に並んでいて、いくらなのだろう?と思って観察していたらお金を受渡している気配がない。見ていたら「無料だよー!」と声をかけられました。なんと。
無料の食事の数々
色んな種類の屋台が出ていて、人々が長い列を作っていました。
▼これはロートチョン?既に売り切れだったのですが、写真を撮っていたらお姉さんがパンダンの麺の新しいパッケージを出してきて『開ける?』という仕草(やさしい…)もったいなかったので断りました><
他にもカオニャオマムアン(もち米にココナッツミルクとマンゴーを載せたタイのおやつ)やカオマンガイ(海南鶏飯)、豚のお肉を載せたものや辛そうな麺など、色々な食べ物がありました。
フリーミールの理由…?
タイ人らしきおじさんになぜ食べ物を配っているのか聞いたら「ブッダが…」しかしあまり聞き取れず…。誕生日ではないはずだし。
「ニューイヤー?」と聞いたらそうだと言っていたので多分旧正月だからだろうと納得したのですが、 もしかしたら違うのかも…。いやそれとも、ブッダが食べ物を施しなさいと言ったとかそういうことなのだろうか。
追記:旧正月がなくても行われているようなので、理由はやっぱりよくわかりません(´・ω・`)
『2010/11/17 -03. バンコク ワット・トライミットとか』 [バンコク]のブログ・旅行記 by hhb00102さん – フォートラベル
今度タイ人かタイに詳しい人と話す機会がある時に聞いてみます…
外国人にも親切なタイのおじさん
おじさんにどこから来たのか聞かれ、「イープンカー」(日本です)と答えたら「アリガトゴザイマス」と言われてちょっと嬉しい。
訪れた外国人に満足してもらいたいという気持ちからか、「お腹いっぱい食べなさい」とお腹をさする仕草をされ、新たなクイッティアオを私のために列を割り込んで(!)取ってきてくださいました…。おじさん、あの、並んでいる人たち…。たくさんいるよ…。
ここに座れるよと案内され、そこで無心にクイッティアオを食べていたらおじさんの姿は消えていました。厚意はありがたいですね。コップンカー。
宗教の役割と機能について思いを馳せる
シーク教の時もそうだったのですが、こういう施しの場を見ていると、自然と宗教とは何だろうと考えさせられます。
食べることというのは原始的な欲求であり命をつなぐ事でもあるので、宗教というもののもとで見返りなく食べ物を振る舞う、というのは、この世界の中でなにか宗教が大きく機能している気がして、普段の人間の行動範囲を超えた善意というか…
私の宗教観
私は意識して何かの宗教に入信したことはないので、宗教を信じるという事がいまいちよくわかりませんでした。
宗教戦争の話なんかを聞くと、宗教は単に人の思考を停止させ所属意識から人と人とを争わせる因子の1つとして利用されているようで、良くないイメージを持ったりもしていました。
ただこのように善意の装置として機能しているところを見ると、そんな単純なものでもないのだなと…
人々の感情の集積装置としての宗教
今日この言葉を急に思いついたのですが、宗教は人々の感情の集積装置としても機能しているのかなと。(『感情』よりももっと適切な言葉があるかもしれませんが、今はちょっと思いつきません。意思とか意図とかだとまた違うし…)
排斥といった悪い感情が集ってしまうこともありますし、今回のように善意や人類愛が集積され機能することもある。宗教という名目なしでは今回のような炊き出しは行われなかったのではないかと思うので。(日本の西成の炊き出しのようなホームレス支援はまたちょっと違いますし)
つまり宗教の存在そのものはいいとか悪いとかではなく、人がどんな感情を集積させるか次第でアウトプットが変わるのかなって。
そう思うと、今までただ避けていた宗教という概念とその機能に興味が出てきました。
宗教の存在理由…?
私が以前思っていたように思考停止の装置として機能しているだけなら、地頭の良い人達が信仰する・後天的に入信するというのも不自然なんですよね。そこには生まれた時の文化以外の理由もあるのではないだろうか。それはちょっと知りたい。
もちろん生まれた時の環境で既にインストールされていて影響が拭いがたい、という状況もあるわけですけど、それにしてもこんなに多くの国で機能しているのだから、きっとなにか意味はあるのだろう。
日本でも他の国でもカルト(反社会的な宗教団体)が人々に害を及ぼす事件はあって、賢い人たちがそれに加担していたり、勧誘が適切ではなかったり、そういう事象もありますけど…
そういった事への拒否反応から宗教を理解しようという行動を取らないのは、それこそ思考停止になるだろうし。
機会があれば教養として宗教学や神学についてもちょっとかじってみたいです。
話がずいぶんそれてしまった。今回はごちそうさまでした(-人-)
▼まだセールをやっている。紙の本価格1,512円のところセールでKindle版が419円(-1,093円)です。
 |
英語で読む 池上彰の世界の宗教が面白いほどわかる本[Kindle版]
池上 彰 KADOKAWA / 中経出版 2014-03-28 |
関連記事